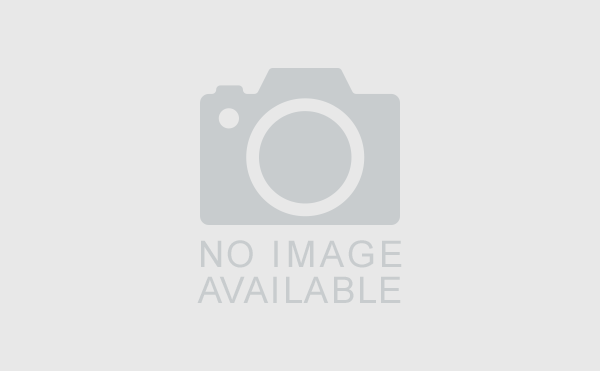行政書士試験 直前期にやることと当日の過ごし方
【5日前〜当日】行政書士試験 直前期にやること|本番で意識したこと(受験実体験メモ)
こんにちは。札幌駅前の行政書士、木村龍生です。
私は令和6年度の行政書士試験受験生です!因みに、模試で一度も合格点を取れないまま本番を迎えました。
それでも本番では一発合格。この記事では、試験直前の5日間の過ごし方と当日の動き方を、実体験をもとに整理しています。
「あと少しで本番…何をすればいい?」と感じている方に向けて、少しでもヒントになればうれしいです。
※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。紹介内容は実体験と一般的な受験ノウハウをもとに構成しています。
筆者について(R6一発合格 → R7開業)
- 令和6年度 行政書士試験 一発合格
- 令和7年 北海道の札幌駅前にて「行政書士りゅうせい事務所」開業
- 主な業務:障がい福祉サービス指定申請・加算整備支援/相続・遺言/許認可申請など
受験と実務の両方を経験して感じるのは、「自信と諦めない心、そして超直前期の対策が結果をつくる」ということ。この記事では、その経験を踏まえて直前期の動きを整理します。
この記事のざっくりまとめ
「もう時間がない…!」と思っている方へ。この記事では、私が試験5日前〜前日までに実際にやっていたことをシンプルにまとめています。
- 📘 直前期の勉強ルーティン
- 👜 前日の準備と持ち物チェック
- 🕊️ 当日に向けたメンタルの整え方
気になるところだけ読んでもOKです。焦る気持ちが少しでも軽くなるように、実体験をもとに書きました。
直前期(残り5日〜前日)にやること
- 模試は1回だけ解く:13〜16時の本番時間に合わせて“雰囲気づくり”。合格点を狙うより、時間の流れと集中の切り替えを体で覚えるのが目的です。
- 仕事をしている人は、できれば1日休みを取る:ベストは金曜日。無理ならOK。短時間でも、机に向かう“感覚”を整えるだけで違います。
- 苦手・誤答の見直し:過去問・模試・テキストで間違えた部分だけを重点的に。「なぜ間違えたか」を見直して、最後は必ず条文で確認。
- 基礎の再確認:行政法の流れや民法の定義など、取りこぼしやすい基礎を再チェック。難問より“確実に取れる問題”を落とさないのが大事。
- 直前チェック本はざっと流す:新しいことは入れず、「見覚えをつける」目的で。不安な部分はテキストや条文に戻ればOK。
- YouTubeやSNSを控える:他人の勉強量を見ると焦るだけ。スマホを遠ざけて、静かな時間を増やすのがおすすめです。
直前期の教材について
新しい教材は増やさず、通信講座と過去問だけを繰り返しました。特に誤答の復習と条文の確認で、知識の抜けを効率的に埋められます。通勤中は音声講義を倍速で流すだけでも十分効果があります。
模試は一度も合格点じゃなかった話
実は、私は直前まで模試で一度も合格点を取れませんでした。それでも本番で点が伸びたのは、最後の数日を「増やさず・整える」時間にしたからです。
- 誤答だけ回す:間違えた肢→講義→条文へ“往復”。
- 判例と条文は見出しだけ:「覚える」より「思い出す導線」を意識。
- 時間配分を固定化:迷う問題は〇をつけて飛ばす練習を。
本番では難問に出会っても深呼吸→次へ。知識を増やすより、“取りこぼさない型”を作る。直前期は、この意識が一番効きました。
前日にやることチェック
- 受験票/腕時計/筆記具/消しゴム/軽食/飲み物/羽織りを確認
- 会場ルートと到着時刻(15〜30分前目安)を再確認
- 苦手・誤答を1回転→早めに切り上げて寝る
- スマホは就寝1時間前にオフ(神経を休める)
行政書士試験 令和7年度 持ち物チェックリスト
忘れ物を防ぐために、前日までに準備を終えておきましょう。必須とおすすめを分けています。
✅ 必ず持っていくもの
- □ 受験票
- □ BまたはHBの鉛筆/シャープペンシル
- □ プラスチック消しゴム
- □ 無音の腕時計(アナログ推奨)
- □ 上履き+下履き袋(会場ルールによる)
- □ 荷物用の透明ビニール袋(床置き抵抗がある方)
🧰 持っておくと安心なもの
- □ 鉛筆削り(手動タイプ)
- □ ハンカチ・ティッシュ・マスク
- □ 羽織り・ひざ掛け(使用時は監督員の許可を受ける)
- □ 目薬・点鼻薬などの体調ケア用品
- □ 飲み物(開始前に軽く水分補給)
- □ 飴やチョコなどの軽食(集中力キープ用)
💡 あると便利な+α
- □ 前日に見る範囲を決めたテキスト・ノート
- □ 予備の筆記具・替芯
- □ 常備薬(胃腸薬・頭痛薬など)
👉 前日の夜にすべてバッグへ入れておくのが安心です。当日は焦らず出発しましょう。
実は、持ち物や準備で少し焦った思い出もあります。時計や飲み物など、意外なところでトラブルになることも。
▶ 受験当日の体験談とちょっとした失敗談はこちら
私はアガルートを軸に勉強して合格しました。
どの講座が合うかは人それぞれなので、資料を見比べてみてくださいね。